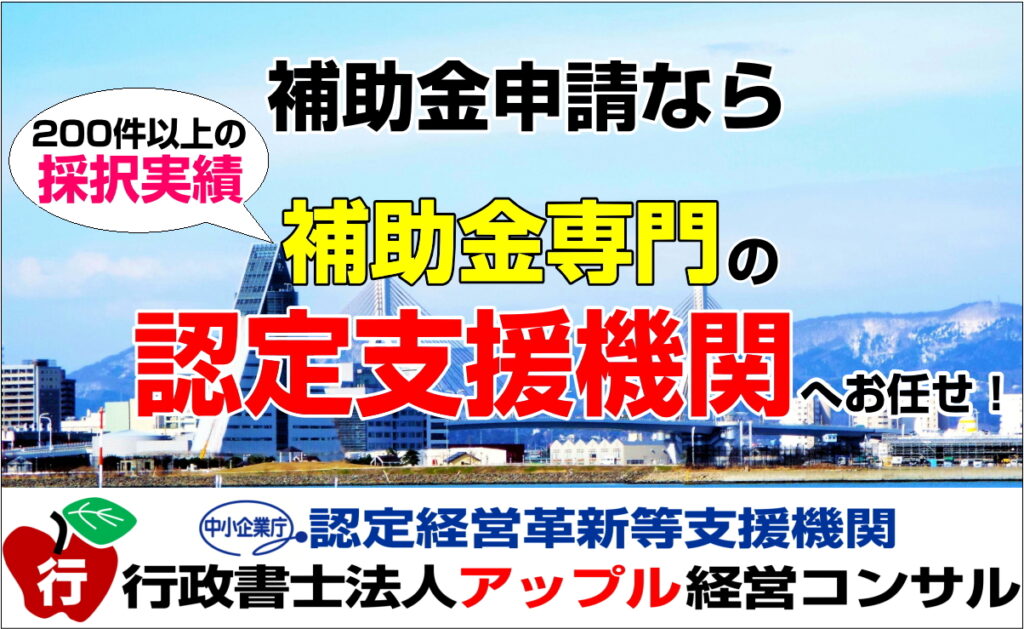中小企業のBCP策定 代行サービス
行政書士が御社の「事業継続力強化計画(BCP)」策定を全面サポート。 自然災害や感染症から会社を守り、補助金申請で有利になる認定取得までワンストップでお手伝いします。

BCP(事業継続力強化計画)とは?
BCPとは、日本語で「事業継続計画」のことです。自然災害やウイルス流行などの緊急時に、被害や損失を最小限に抑えるための計画を指します。 あらかじめBCPを策定しておくことで、緊急時の混乱を防ぎ、被害や損失を抑えることが可能になります。 しかし実際には、多くの中小企業でBCPは未策定のままです。 中小企業庁の調査によれば、2022年における中小企業のBCP策定率はわずか22.0%でした。 主な理由は「策定に必要なノウハウがない」「策定する人材を確保できない」などですが、いざという時に事業を守るためにはBCPの策定が不可欠です。なぜBCPが必要か
BCP策定が重要視されるのには、以下のような理由があります。- 事業の早期復旧: 大規模災害や事故で長期間事業を中断すると、中小企業にとって致命的な打撃となりかねません。 BCPで何を優先するかを決めておけば、有事でもすみやかに事業を復旧・継続でき、倒産のリスクを大幅に減らせます。
- 取引先・顧客の信頼維持: 非常時に適切な対応ができず事業停止となれば、社会的な信用を損なう可能性があります。 BCPを備えている企業は、緊急時でも安定して経営を継続できるため、取引先からの信頼性が高まり、取引の継続や新規契約獲得につながります。
- 従業員の安全確保と雇用維持: BCPには従業員の安全確保策も含まれます。 災害時でも従業員の命と生活を守り、事業を継続できれば雇用も維持されます。 結果的に従業員の安心感や会社への信頼感も向上します。
- 増大するリスクへの備え: 近年は自然災害の多発やパンデミックなど、事業継続を脅かすリスクが高まっています。 平時からBCPを策定し訓練しておくことで、有事の被害を最小限に抑えることが可能です。
BCP策定のメリット
- 経営判断の迅速化: 緊急時の判断基準が明確になることで、経営者の意思決定が素早く的確になります。
- 信用力・資金調達力の向上: BCPを策定することで企業の信用力が高まり、取引先との信頼関係が強化されます。 また、事業の継続性が担保されることで金融機関からの評価も向上し、資金調達がしやすくなります。
- 業務改善と効率化: BCP策定の過程で自社の業務を見直すことで、平常時には気づかなかった非効率なプロセスや潜在リスクを発見し、経営改善に活かせます。 また、限られた経営資源を重要業務に集中させることで、有事でも効率的に事業を継続できます。
- 地域との連携強化: BCPを策定することで地域の企業や自治体との協力体制を構築でき、災害時に相互支援が可能になります。 地域全体の防災力向上に貢献でき、地域社会からの信頼も獲得できます。
- 補助金申請での加点:国の補助金のうち、ものづくり補助金、省力化投資補助金ではBCPが認定されると審査時に加点となります。 この加点が、補助金の採択(合格)に大きなハンディキャップとなります。
BCP策定のステップ
- 基本方針の策定: BCP策定の目的や優先事項を明確にし、経営方針に沿った事業継続の基本方針を定めます。 例:従業員の雇用を守る、顧客の信用を守る など。
- 重要業務の特定: 緊急時に優先的に継続すべき自社の中核事業や重要な商品・サービスを洗い出します。 例:複数事業を展開している場合でも、有事には主力事業に集中し、「主要顧客向け製品A」のように事業継続に欠かせないサービスを特定します。
- リスクと被害の想定: 想定される危機(地震、風水害、パンデミック等)ごとに自社への影響(設備被害、人員不足、物流停止など)を分析します。 例:地震なら建物や設備の損傷、感染症なら従業員の出勤困難による人手不足、といったシナリオを想定して対策を検討します。
- 事前対策の実施: 人・物・金・情報といった経営資源ごとに、事業継続のための事前対策を講じます。 例:人=安否確認ルール整備と代替要員確保、物=設備の耐震・防災対策と代替拠点の確保、金=必要資金の把握と緊急時の資金調達先確保、情報=データバックアップと非常時の情報通信手段確保。
- 緊急時体制の構築: 非常時の指揮命令系統や役割分担を定め、社内の緊急対応体制を整備します。 例:社長をBCP発動の責任者とし、代行の幹部も指定。従業員・顧客の安否確認、取引先への連絡、対外情報発信、資金確保など、緊急対応手順を策定します。
補助金・公的支援制度との関係
BCPを策定し認定を受けることで、企業は自社の強靱化だけでなく公的な支援策も活用できます。中小企業が策定した防災・減災に関する計画を「事業継続力強化計画」として国(経済産業大臣)が認定する制度があり、認定企業には以下のような優遇措置が用意されています。- 低利融資や信用保証枠の拡大などの金融支援
- ものづくり補助金など各種補助金申請時の優遇(加点措置・優先採択)
- 防災・減災設備投資に対する特別償却などの税制優遇
- 自治体による認定企業向けの助成金・支援制度
- 中小企業庁ホームページでの認定企業名公表(信用力向上)
- 認定ロゴマークの使用許可(会社案内や名刺・Webサイト等でPR可能)
業種別のBCP活用事例
実際にBCPを策定・活用している中小企業の事例をいくつかご紹介します。製造業の事例
包装資材製造のA社では、2009年の新型インフルエンザ流行を契機にBCPを策定しました。全社員にBCPポケットマニュアルや大地震初動対応カードを配布し、避難訓練のたびに計画を見直しています。 また、バネ製造のC社では、会社が海岸近くに立地していることから東日本大震災の教訓を踏まえて対策を実施。社員とその家族の安否確認システムを導入し、県外企業との相互応援協定を締結するなど、防災体制を強化しました。建設業の事例
ある建設会社では、熊本地震をきっかけにBCPを見直しました。データのバックアップ、発電機の用意、代替拠点の確保などを行い、年2回の社内訓練を実施しています。 また、ある工務店では、大型台風による被害の教訓から災害対応マニュアルを作成し、台風が発生するたびに改定を重ねました。その結果、熊本地震では前震の翌朝から修理や安全点検を開始し、早期にグループ会社と連携して必要な人材・物資の確保に成功しました。サービス業の事例
あるサービス業では、取引先工場の停止や通信遮断を想定したBCPを策定しました。独自のデータバックアップシステムを構築し、被災時に備えた備品の用意や運用訓練などを実施し、年に1度BCPの内容見直しと備品点検を行っています。 その結果、非常時にも主要サービスの提供継続が可能となり、取引先からの信頼維持に成功しています。BCP導入後の効果
BCPを策定・導入すると、万が一の際に確かな効果を発揮します。2016年の熊本地震では、BCPを策定していた企業が事業継続に成功した事例が多数報告されており、有事に備えた取り組みの重要性が改めて示されました。 大災害発生時に競合他社に先んじて事業を復旧できれば、取引先からの信頼を守るだけでなく、災害後の市場ニーズも獲得できるでしょう。 また、BCPの認定取得により得られる信用力向上は、平時の営業面でもプラスに働きます。自社が中小企業庁の認定企業リストに掲載され、名刺やホームページに認定ロゴを表示できるため、「防災に真剣に取り組んでいる会社」として対外的な信頼性が高まります。 さらに、副次的な効果として損害保険料の割引があります。事業継続力強化計画の認定企業のリスク実態に応じて、損害保険会社では保険料の割引サービスが提供されており、BCP導入が保険コストの削減にもつながっています。料金プラン
ライトプラン
BCP策定の簡易サポートプランです。ヒアリングシートにご記入いただいた内容をもとに、事業継続力強化計画書のドラフトを作成します。- 初回ヒアリング(オンライン1回)
- BCP雛形の提供・策定アドバイス
- 事業継続力強化計画書(ドラフト版)の作成
- 認定申請書類の準備サポート
料金: 7万円(税別) 弊所で補助金も一緒に申請する場合、3万円(税別)
スタンダードプラン
BCP計画書の作成から認定申請までをフルサポートする基本プランです。対面またはオンラインでの詳細ヒアリングを通じて、リスク分析から計画策定、申請書類作成まで弊所が代行いたします。- 詳細ヒアリング&リスク分析の実施
- BCP(事業継続力強化計画)計画書一式の作成代行
- GビズID取得サポート・電子申請代行
- 認定結果に応じた修正・再申請サポート
料金: 20万円(税別)
プレミアムプラン
策定後の運用まで支援する充実プランです。スタンダードプランの内容に加え、BCPの社内浸透や定期的な見直しまで継続サポートします。訓練の実施や補助金を活用した防災対策導入支援も含まれます。- BCP社内説明会・従業員向け訓練の実施支援
- 策定後の運用サポート(年1回の計画見直し同行)
- 防災対策実施のフォロー(補助金活用アドバイス)
- 認定取得保証(万一認定不可の場合は全額返金)
料金: 50万円(税別)
※ 上記料金は目安です。企業規模や事業内容により追加費用をお願いする場合があります。正式なお見積りはお問い合わせ後にご提示いたします。
よくある質問
- BCPと事業継続力強化計画は何が違いますか?
- 「事業継続力強化計画」は、中小企業が策定するBCP(事業継続計画)を国(経済産業省)が認定する制度です。平時の防災・減災対策について計画書を作成し、中小企業庁に申請して認定を受けることで、税制優遇や補助金加点などの支援策が受けられます。 平たく言えば、BCPを国のお墨付き付きで策定するのが「事業継続力強化計画」です。
- 事業継続力強化計画の認定取得にはどれくらい時間がかかりますか?
- ヒアリングから計画書ドラフト完成までは通常1~2ヶ月程度です。その後、認定申請を行ってから審査・認定まで標準で約45日間を要します。全体では、おおむね3ヶ月前後で認定取得が可能です。
- 小規模企業でもBCPを作れますか?知識がなくても大丈夫?
- もちろんです。事業継続力強化計画の認定制度は中小企業・小規模事業者が利用できます。BCPの専門知識がなくてもご安心ください。弊所がヒアリングを通じてリスク分析や計画策定をサポートし、分かりやすくアドバイスします。
- BCP策定には補助金や助成金を使えますか?
- BCP策定そのものを支援する国の補助金は現在ありません。ただし、自治体によっては策定支援の助成制度があります。例えば、東京都の「BCP実践促進助成金」は策定したBCPに基づき必要な防災備品等の導入費用の一部を助成しています。 また、愛知県豊橋市など一部自治体では、BCP策定費用自体に対する助成金制度もあります。最新の募集状況は各自治体や商工会議所にご確認ください。
- BCPを策定した後、何をすればいいですか?
- BCPは作って終わりではありません。策定後は計画を社内に浸透させ、定期的に訓練を行うことが重要です。非常時に備え、従業員全員が安否確認や非常用電源の操作方法などを習熟できるよう、年1回以上のBCP訓練・計画見直しを実施しましょう。 弊所のプレミアムプランでは、策定後の訓練や運用改善まで継続サポートいたします。
BCP策定の依頼なら
弊所は経済産業省の認定支援機関として、全国の中小企業の皆様に経営革新計画の策定を行っています。 また、行政書士法人として、国の補助金の事業計画書作成や電子申請などの支援を行っています。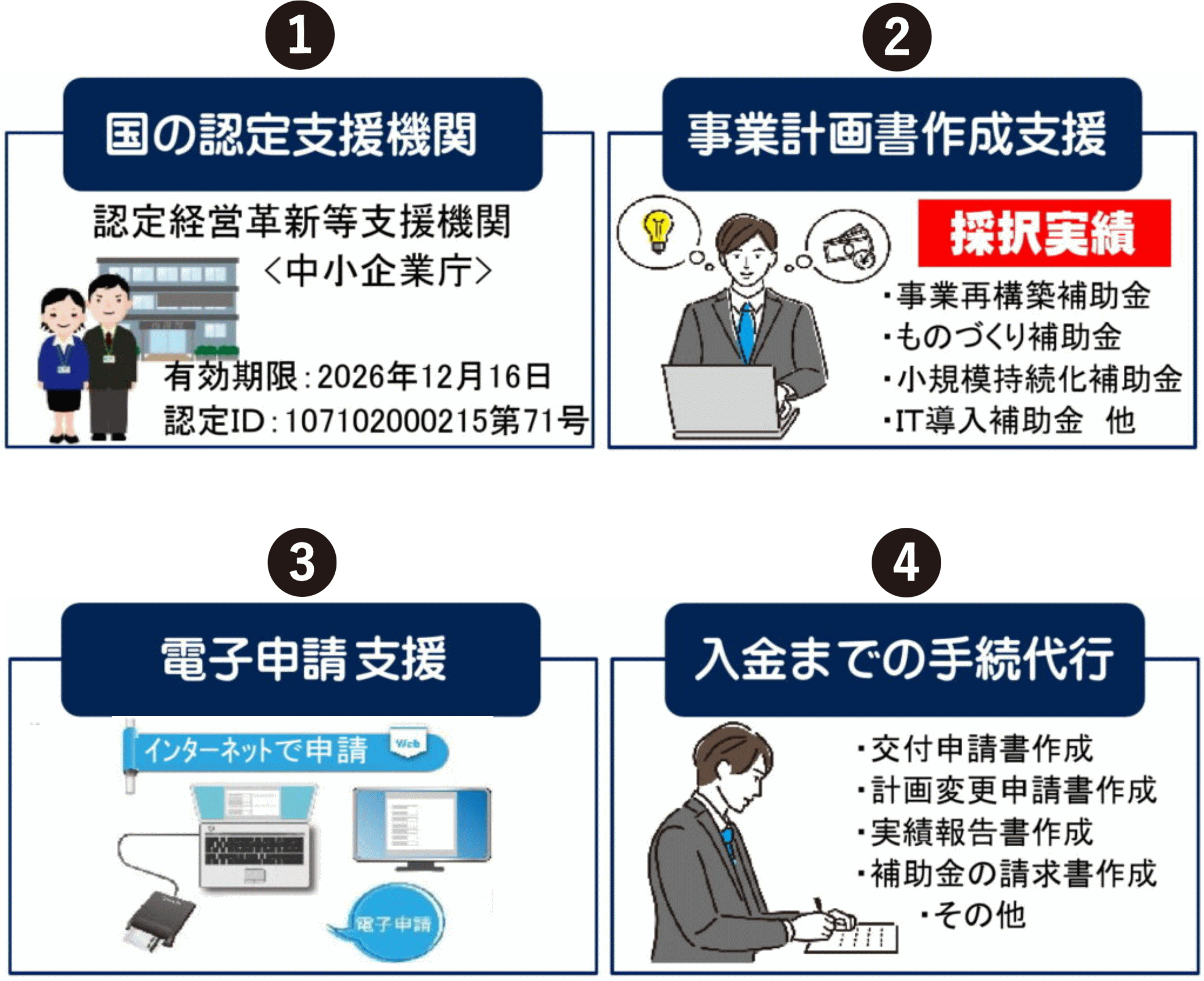
| 行政書士法人アップルの実績 |
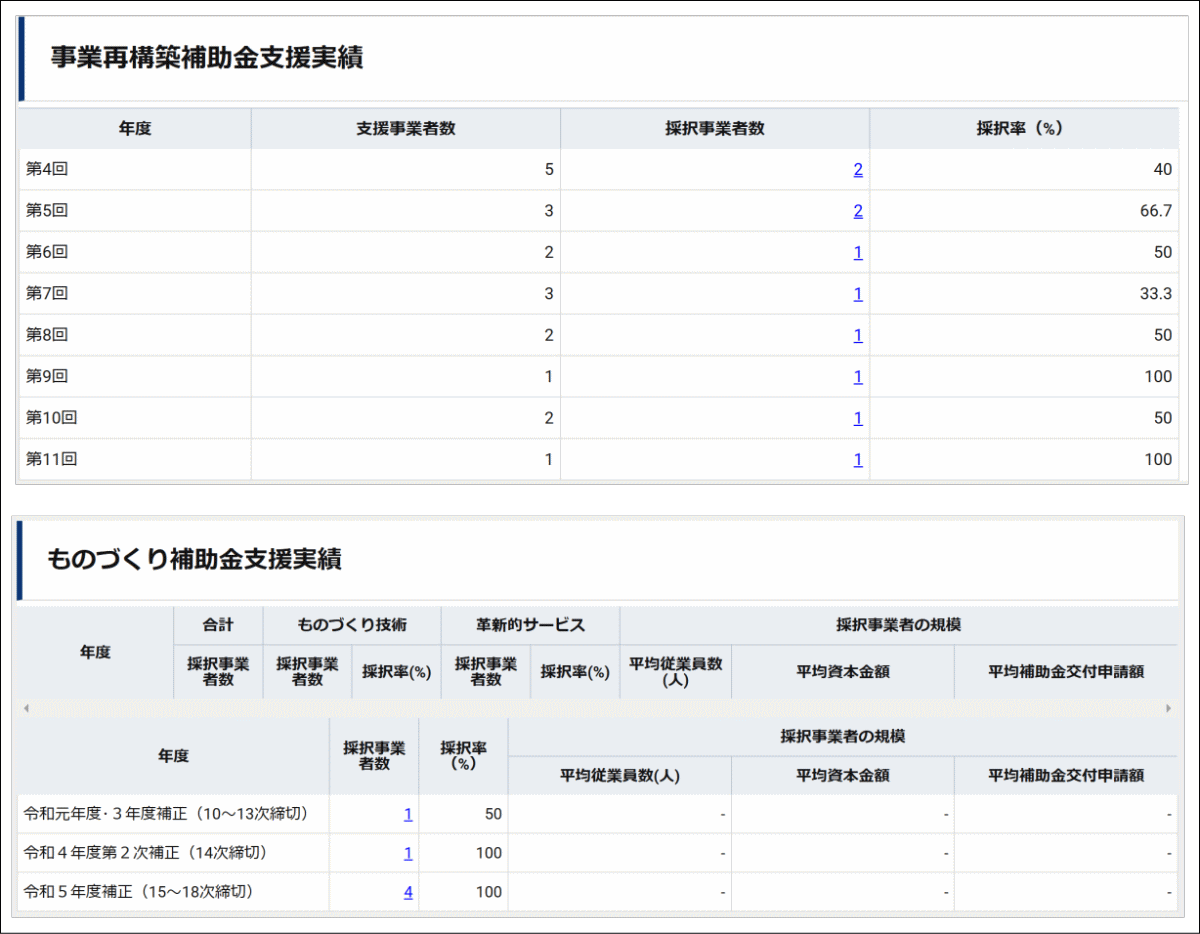
| 助成金名 | 応募数 | 採択数 | 採択率 |
| 事業再構築補助金 | 25 | 16 | 64 (%) |
| ものづくり補助金 | 8 | 7 | 88 (%) |
| 計 | 33 | 23 | 70 (%) |
| 支援した事業者様の採択事例 |
この採択事例は、省力化補助金の前身「ものづくり補助金」省力化オーダーメード枠のものです。
この時の全国の採択率は34.0%と難関でしたが、当社では100%採択されました。 下記が採択された事業計画書ですので、このくらいのレベルで採択基準に達すると思われます。
貴社とともに事業計画書の作成を支援いたしますので、ご安心ください。
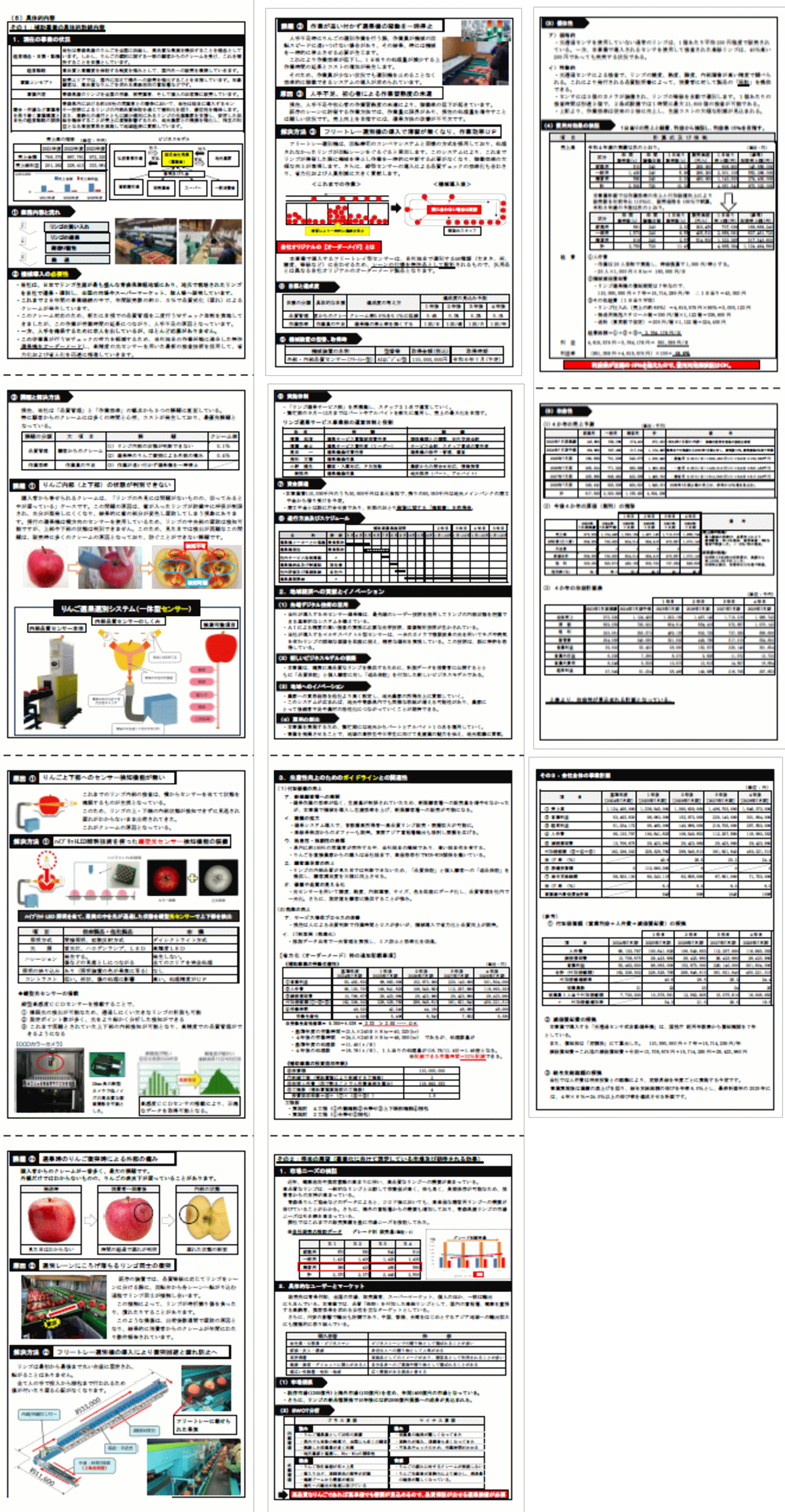
| BCP事業継続力強化計画の料金プラン |
| プラン名 | 内 容 | 料 金 |
| ライトプラン | BCP策定の簡易サポートプランです。ヒアリングシートにご記入いただいた内容をもとに、事業継続力強化計画書のドラフトを作成します。 とりあえず補助金の加点用に取りたい場合用です。 | 60,000円 ※弊所で補助金と一緒に申請する場合は、30,000円に割引します。 |
| スタンダードプラン | BCP計画書の作成から認定申請までをフルサポートする基本プランです。対面またはオンラインでの詳細ヒアリングを通じて、リスク分析から計画策定、申請書類作成まで弊所が代行いたします。 | 200,000円 |
| プレミアムプラン | 策定後の運用まで支援する充実プランです。スタンダードプランの内容に加え、BCPの社内浸透や定期的な見直しまで継続サポートします。訓練の実施や補助金を活用した防災対策導入支援も含まれます。 | 500,000円 |
| 電子申請サポート料金 | 電子申請が苦手な方をサポートします。 | 事業者様の申請が基本ですが、ZOOM等でサポートします。 |